大学受験はとにかく不安との戦いです。
「全然成績が上がらない、、、」
「自分に難関大学なんて無理、、、」
「底辺高校から大学なんて、、、」
このような不安に押しつぶされそうな受験生も多いことでしょう。
しかしみなさん安心して下さい。
自分を見失わず最後までしっかり勉強を続ければ、自分がどんな高校に通っていようと、今自分の偏差値がどれだけ低かろうと、きっと合格出来ます。
実際に私は、偏差値40という底辺高校に通っていましたが、学校創立以来90年の歴史で初めて旧帝大に合格することが出来ました。
この記事では、私の逆転合格エピソードをご紹介し、みなさんの不安を少しでも和らげ、希望を持って頂ければと思います。
逆転合格するために必要なこともご紹介しますので、みなさんの参考になれば幸いです。
もくじ
底辺高校から難関国立大学への逆転合格エピソード

受験を意識した高2の冬
12月
高2の12月に担任、保護者、私の3者面談が開催。
普段から親と進路をしてこなかった私は、そこで初めて自分が「大学進学したい」ということを担任と親に告げました。
大学進学したかった理由は「まだ働きたくなかったから」。
「大学進学は当たり前だろう」と思われるかもしれませんが、私が通っていた高校の偏差値は40。
学年の内4年制大学に進学する人は半数しかおらず、その内一般入試を受験する人は3割ほどです。
大学受験する人は学年全体でたったの1割しかいません。
3者面談が終わった後帰り道で親から言われた衝撃の一言。
「うちにはお金がないから大学は国公立しか行かせられへんからな」
こうして私の大学受験は始まりました。
1月
これまで全く勉強してこなかった私はいきなり大学受験と言われても何から始めたら良いか分かりません。
高校の先生も大学受験の指導経験がほとんどないし、ましてや国公立大学の受験に関しては全く頼りになりませんでした。
なぜなら私の高校から創立以来80年以上、国公立大学に進学した人がいないからです。
私の高校の合格実績と言えば、数年に一人天才と呼ばれる生徒が「産金甲龍」に合格するくらいです。
「関関同立」なんて神の領域で、10年に一人いるかいないかです。
こんな状況から国公立大学を目指したのは無謀ですが、無知ゆえに不可能と考えずに挑戦できたのは、今思えば幸運でした。
とりあえず本屋に向かって、参考書を探していると運命的な出会いをしました。
『和田式高2からの受験術』という本です。
逆転合格するための方法が細かく紹介されています。
非進学校から難関大学に合格する方法も掲載されており、正に自分のための本だと感じました。
今は絶版になっていますが、そのエッセンスを織り込んだ勉強法・勉強スケジュールは以下の記事で紹介しています。
絶対参考になると思うので、ブックマークだけして後で読むようにしてください。
この本の内容に沿って勉強計画を組み立てました。
まずは目標設定から。
家から通える一番簡単な国公立である大阪府立大学(22年4月から大阪市立大学と合併)を志望校にして対策を考えました。
大阪府立大学の共通テストの科目は「国語、英語、数学、日本史」で、二次は「英語、数学」でした。
3月
当時はがっつり週3〜4日飲食店のバイトが入っており勉強時間が確保できなかったため、バイトを辞めました。
結局、本格的に勉強を開始したのは高2の3月になってからでした。
中学生の時もろくに勉強せず、高校受験もほぼノー勉だった私は中学生レベルからやり直す必要がありました。
市販されている一番簡単な参考書から取り組みました。
大岩のいちばんはじめの英文法【超基礎文法編】
高校これでわかる数学I+A
使った参考書はコレです。
かなり丁寧で分かりやすい参考書で、偏差値40の底辺高校で中の下の成績しかない私でも理解できました。
ただ、これまで全く勉強してこなかった私が急に勉強できるわけもなく、1日数十分〜1時間勉強するのがやっとでした。
そのため、この入門の参考書を終えるだけでも数ヶ月(高3の5〜6月まで)かかりました。
高3
春
春になってベネッセの『進路マップ』という実力テストを受けました。(進研模試より更に簡単な模試で、商業高校や工業高校しか受けません。)
1ヶ月勉強しただけなのに学年で学年150人中100番目くらいだったのが、学年3位まで一気に躍り出ました。
「たったこれだけの勉強でごぼう抜き出来るなんて、どんだけ高校のレベル低いんだ、、、」とも思いましたが、勉強の成果が出て自信も出てきました。
夏
この時期になってようやく勉強習慣が身についてきました。
毎日1〜2時間くらい勉強できるようになりました。
これまで全く勉強してこなかった人間がすると信じれない快挙です。
母親が本気で驚いていました笑
超基礎レベルの参考書も無事に終えて、本格的に基礎固めに取り組んだ時期です。
ビジュアル英文解釈
青チャート
この二つの参考書は私の英語と数学の絶対的な基礎となり、私の自信の源になりました。
この参考書はめちゃくちゃオススメです。
そんな折、進路相談のための三者面談がありました。
私がこの場で担任の先生に志望校(大阪府立大学)を告げると
「お前になんか無理や!」
と驚きの反応が返ってきました。
当時私が反抗的な生徒だったということもあって担任と仲が良くありませんでした。
それでも生徒に対してこんな酷いことを言うのは今考えればありえないですね。
怒りと悔しさで泣きそうになりましたが、この発言で私の気持ちに火が付きました。
「絶対に見返してやる」
そう思ってこの日から勉強時間を増やしました。(それでも1日2〜3時間ですが笑)
秋
普通の高校ではあり得ないことですが、私の高校では数学Bの履修がありませんでした。
なので完全独学で取り組む必要があり、高3の秋からようやく数学Bの勉強を開始しました。(今考えると遅すぎる笑)
参考書は「面白いほどわかる」シリーズを使いました。
面白いほどわかる
また「そろそろ共通テストの対策をしないと、、、」と考え日本史の勉強を始めました。
日本史の勉強は教科書をひたすら読みました。(この勉強法は完全に失敗でした)
詳説日本史B
-

-
「覚えることが多すぎる、、、」日本史選択で後悔した時はどうすればいい?
続きを見る
関連記事:「覚えることが多すぎる、、、」日本史選択で後悔した時はどうすればいい?
この頃から焦りと不安がかなり強くなってきました。
青チャートの問題数が膨大過ぎて一向に終わらず、英語に関しても英単語が覚えきれず長文がなかなか読めるようにならなかったからです。
「もっと早く始めればよかった、、」「もっと勉強時間増やせばよかった、、」
後悔ばかり頭をよぎりました。
不安が強くなると勉強に集中できなくなって余計に不安が大きくなるという完全に悪循環に陥ってました。
センター試験(共テ)〜二次試験
12月になるといよいよ受験という感じがして焦りと不安がピークに達しました。
模試や過去問を解いても全く点が取れず、志望校に合格するイメージが全く持てません。
全く自信がないまま共通テストに突入。
案の定爆死して、65%しか取れませんでした。
例年の合格最低点は何とか上回っていたものの、記述力に全く自信がありません。
この頃からすでに諦めモードで、浪人を視野に入れ始めてました。
一度逃げの選択肢を意識すると、なかなか集中して勉強することが出来なくなります。
二次試験まで1ヶ月半時間がありましたが、勉強が身に入らず1日3時間程度の勉強時間でした。
そして試験本番。
淡い期待を抱いていましたが、結果は不合格。
自分なりに頑張ったつもりだけど、圧倒的に勉強不足でした。
不合格の要因は紛れもなく勉強不足です。
大阪府立大学の前期しか願書を出していなかったので、浪人生活に突入です。
-
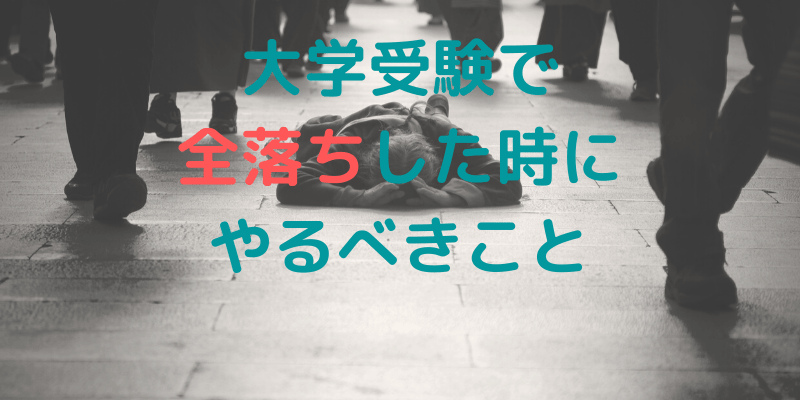
-
大学受験で全落ちした時は?しっかり反省すれば必ず逆転出来る!
続きを見る
関連記事:大学受験で全落ちした時は?しっかり反省すれば必ず逆転出来る!
浪人(宅浪)
春
お金がなく予備校に通えないので必然的に宅浪を選択。
「宅浪で成功するヤツはいない」というネットの情報ばかり見てかなり不安でした。
ただ、今思えば宅浪したおかげで阪大に逆転合格できたのだと確信してます。
この時は志望校はかなり保守的に「大阪府立大学に合格できれば十分」と考えていました。
不合格になって精神的にも疲れてましたが、ここで怠けてしまうと浪人中ずっとサボってしまうと考え、不合格になって1〜2週間後には勉強を開始。
宅浪中は平均して1日7〜8時間勉強しました。
宅浪中の1日のスケジュールは以下記事でまとめてますので、参考にどうぞ。
-

-
宅浪を成功させる6つのコツ。自宅浪人で底辺高校から阪大に合格
続きを見る
関連記事:宅浪を成功させる6つのコツ。自宅浪人で底辺高校から阪大に合格
現役時代は時間がないので参考書をとにかく進めることしか意識せず、知識が定着せずに失敗しました。
宅浪は時間がたっぷりあるので、まずは現役時代にやった参考書の解き直しから始めました。
具体的には、『ビジュアル英文解釈』と『青チャート』を完璧にするまで繰り返します。
ビジュアル英文解釈
青チャート
また、宅浪でちゃんと勉強できるか不安だったので、ペースメーカーとしてZ会を始めました。
これがかなり良い選択となり、宅浪中に劇的に成績が伸びるようになりました。
-

-
偏差値40からZ会だけで旧帝大に合格!大学受験でZ会をおすすめする理由
続きを見る
関連記事:偏差値40からZ会だけで旧帝大に合格!大学受験でZ会をおすすめする理由
夏
現役時代にやった参考書をやり直したおかげで基礎がかなり固まります。
浪人というアドバンテージはありましたが、ここでじっくり基礎固めをやったおかげで、夏以降一気に偏差値が急上昇しました。
やっぱり基礎はめちゃくちゃ大事です。
夏からは現役時代にはできなかった演習問題に取り組みました。
演習問題で一番解いた問題は『英語長文問題精講』と『文系数学の良問プラチカ』です。
英語長文問題精講
文系数学の良問プラチカ
『英語長文問題精講』は人によってかなり好みが分かれます。
文章がかなり古臭く、構文の解釈がかなり難解なので読み進めるのに非常に苦労しますが、だからこそこの参考書をマスターする頃には英語に絶対的な自信を持つことが出来ました。
『文系数学の良問プラチカ』は難関国立大学(文系)を目指す人全員におすすめしたいです。
青チャートでは各単元ごとに独立した問題が出題されていましたが、『文系数学の良問プラチカ』では複数の単元の知識を組み合わせないと解けない応用問題が出題されています。
またこの頃から共通テストの科目である政治経済の勉強を始めました。
秋
秋になると正直かなり疲れてきました。
いわゆる中だるみです。
「本当に合格できるのか?」
「浪人しているからもう後がないぞ、、」
このように焦りと不安が強くなった時期でもありました。
それでも模擬試験を受けると偏差値が上がっていたので、なんとかモチベーションを保ち続けることが出来ました。
共通テストの理科科目の地学はこの頃から手をつけました。
地学は短時間で8割取れると聞いて実践しましたが、その通り短期間の勉強で本番85%取れました。
-

-
共通テスト(センター)地学基礎の勉強法とおすすめ参考書【一ヶ月前でOK】
続きを見る
関連記事:共通テスト(センター)地学基礎の勉強法とおすすめ参考書【一ヶ月前でOK】
センター試験(共テ)〜二次試験
いよいよ共通テストが近づいてきました。
この時点での私の志望校は「大阪市立大学」です。
模試の結果では更に上を目指せることが分かっていましたが、偏差値40の底辺高校出身ということもあって、自分が国公立大学に合格できるのか未だ半信半疑だったからです。
これまでずっと二次試験対策しかしてこなかったため、12月くらいから共通テスト対策をしました。
二次試験対策で実力がかなり身についていたため、共通テストの試験形式に慣れれば8割は大体超えるようになりました。
そんな状況で迎えた共通テスト。
結果はなんと85%。
大阪市立大学志望だったのが、一気に大阪大学まで射程圏内に入りました。
ここから本気で阪大を目指し、過去問を解きまくります。
また、私立は関西学院大学と同志社大学を受験しました。
結果は余裕の合格。
同志社大学に至っては、40度近くの高熱というコンディションが最悪の状態で試験を受けたのですが、問題がめちゃくちゃ簡単に感じました。
この時「自分の実力は本物」と確信し、阪大にも合格できるという自信が漲りました。
迎えた大阪大学の二次試験。
英語と数学と国語の3科目ですが、これまでの勉強の成果を存分に発揮できました。
自己採点して6割以上、かなり厳しめに採点しても5割は超えてます(例年の合格最低点は5割)。
それでも結果発表まで自分が合格している姿が想像できず不安でした。
そして、結果発表。
合格発表は朝9時からですが、前日緊張で寝れず深夜までアニメを見ていたため、朝11時くらいに目を覚まします。
受験票を手にしてパソコンの前に座り、深呼吸して大阪大学の合格発表のページを開きます。
自分の受験番号を探して、、、「あった」思わず声が漏れます。
「よっしゃぁぁぁぁ!!!!!」
あまりの嬉しさに叫びました。
そして「底辺高校から大阪大学に合格する」という1年前の自分が全く想像してなかったことをやり遂げたことに段々と実感が湧いてきて、しみじみと喜びを感じていました。
これから待つ華やかな大学生活に心を躍らせながら、私の長いようで短かかった大学受験が終わりを告げました。
こんな底辺高校に通っていた私ですら難関大学に受かるのです。
正直、難関大学に合格することは難しくありません。
私より偏差値の高い高校に通っている受験生の皆さんにとっては、なおさら簡単でしょう。
私の合格体験記を読んで、底辺高校に通う受験生のみならず、難関大学を目指す受験生の方にも、「こんな奴でも合格できた」と、自信と希望を持ってもらえたら嬉しいです。
なぜ底辺高校から旧帝大に逆転合格できたか

ここからは、私がなぜ偏差値43の底辺高校から旧帝大に合格出来なのかをご説明します。
みなさんは大学受験で重要なことは何だと思いますか?
才能でしょうか?努力でしょうか?それとも気合でしょうか?
どれも大事なことですが、私は「継続」と「戦略」が一番大切だと考えます。
実は私は現役時代に全落ちしました。(と言っても受けたのは大阪府立大学前期日程のみ)
原因は明らかで、圧倒的な勉強不足です。
1日数時間も継続して勉強することすらまともに出来ず、結果は惨敗でした。
この失敗を糧に、浪人時代に意識したことは「勉強を継続する」ことです。
また、ただ継続するだけではダメです。
圧倒的に不利な状況から逆転合格を勝ち取るためには、「戦略的に勉強する」必要があります。
継続的に且つ戦略的に勉強した結果、成績が急上昇し、志望校にするなど考えもしなかった大阪大学に逆転合格することが出来たのです。
浪人生だから長時間勉強したのだろうと思うかもしれませんが、実は浪人時代は1日7時間程しか勉強してません。
私の集中力ではこれが限界でした。
それでは、逆転合格を可能にした「継続」と「戦略」について詳しくご説明していきます。
逆転合格に必要な「継続」というスキル
文房具メーカー「ぺんてる」が行った調査によると、東大生の合格者の65.9%が「毎日」勉強していたそうです。
「あなたが高校生時代に行っていた勉強頻度をお答えください」という質問に対し、
普段の勉強頻度は、「毎日」が57.0%で圧倒的No.1となった。特に東大生に関しては、65.9%と、6割強の人が、毎日コツコツ勉強していたことが判明した。
「東京六大学卒業生・在校生調査」
この数字を多いと見ますか、少ないと見ますか?
私は「少ない」と思います。
難関大である東京6大学の合格者でさえ、毎日勉強している人は57%です。
東大でさえ、66%です。
毎日勉強するだけで、残り半数近くのライバルに優位に立つことができます。
それも優れた戦略を立てて、より効率的に勉強することが出来れば、一気に合格に近づきます。
毎日勉強する、それだけ合格に近づくのです。
ライバルは思ったほど強くはありません。
ただ勉強を毎日する、継続する、勉強の習慣を定着させるのは難しいですよね。
実際私も現役時代に継続して勉強することが出来ず全落ちしてしまいました。
私が毎日勉強を継続させるために意識したことは以下の3つです。
- 通信教育をペースメーカーとして使う
- 家で集中して勉強できる環境を整える
- どうしても気分が乗らないときは場所を変える
順番にご説明します。
通信教育をペースメーカーとして使う
宅浪時代に「通信教育」を始めることで、継続的に勉強することが出来ました。
通信教育でなんで継続して勉強できるようになるの?
このような疑問を持つ方と思いますが、通信教育は「ペースメーカー」として非常に効果的です。
私は勉強習慣を定着させるのに「Z会」をフル活用しました。
Z会はインプット、アウトプット、フィードバックというサイクルが毎月繰り返されます。
このサイクルが受験勉強のペースメーカーとして非常に有効なのです。
添削問題は月1〜2回の提出なのですが、毎月「添削問題を解く」というゴールに向けて勉強計画を組み立てることになります。
これが一種の強制力となり、勉強習慣の定着化に非常に効果的です。
ペースメーカーとして非常に優れているため、Z会をベースに勉強計画を組み立てることが出来ます。
ゴールと計画が決まっていれば、「今日はどの勉強をしよう」と迷うことがありません。
「勉強する」という行動の前の準備行動、これがやる気を無くす原因となるのです。
「どの科目を勉強するか」という些細な悩みでも、やる気をそぎ、行動を鈍らせる原因となります。
添削問題を提出するという強制力と、Z会を受けるだけで半自動的に定まる勉強計画によって、簡単に「継続して勉強する」ということが達成できるのです。
私は実際に浪人してからZ会を始めることで、勉強を習慣化することが出来ました。
-
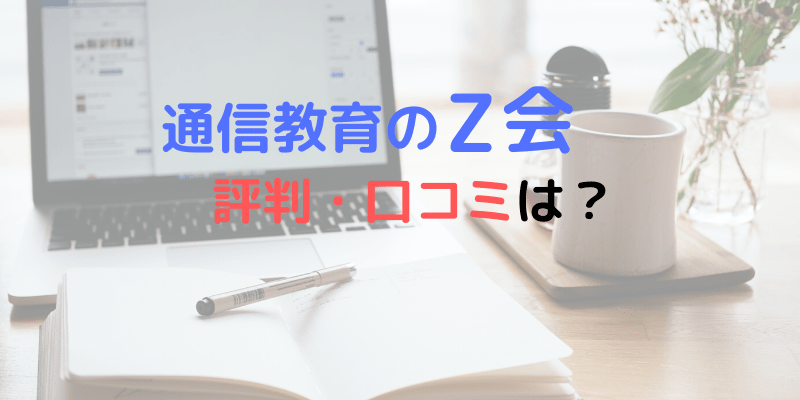
-
【実体験レビュー】Z会大学受験・高校生の評判と口コミを実際に利用して徹底調査
続きを見る
関連記事:【実体験レビュー】Z会大学受験・高校生の評判と口コミを実際に利用して徹底調査
家で集中して勉強できる環境を整える
「家だとなかなか勉強できない、、、」という人は多いんじゃないでしょうか。
私も受験生の頃はそうでした。
ただ、家で長時間勉強できるようにならないと詰みます。
塾や予備校に通おうが、結局いかに自習時間を確保できるかが合否の分かれ目になります。
家の中が勉強の邪魔したり、サボることへ誘惑するものばかりだと、集中して勉強できないので本当に危険です。
以下の記事で、家でも集中して勉強できるようになるコツと環境づくりについて解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
-

-
家で勉強できないのは甘えじゃない。簡単に集中できる2つのコツ
続きを見る
関連記事:家で勉強できないのは甘えじゃない。簡単に集中できる2つのコツ
どうしても気分が乗らないときは場所を変える
どれだけ家の環境を整えたとしても、受験は長期の戦いなので時にはどうしても勉強する気が起きない時もあります。
勉強をサボりたい時に甘えてしまうのか、少しでも勉強時間を確保するのかで結果は大きく変わります。
おすすめなのが、家以外に集中して勉強できる場所を知っておくことです。
勉強道具を持って、カフェでもファミレスでも図書館でも、どこか椅子とテーブルがある環境に行くと自然と勉強する気力が湧いてきます。
なぜなら、外に出た時点で勉強するという行動が始まっているからです。
勉強ってやり始めるまでが一番めんどくさいんです。
逆に机の前に座り参考書をひらけば、あとは惰性でなんとか勉強できます。
つまり最初のスタートさえ切ることができれば、自然と苦もなく勉強することができるのです。
勉強したくない時って、「机の前に座るのさえ嫌、、、!」という気分だと思います。
この「机の前に座る」という勉強のスタートを、「家を出る」という別の行動に置き換えます。
やる気が出ない時に気分転換がてら家を出るだけで、あとは転がるように勉強に進んでいくのでおすすめです。
おすすめの勉強場所は以下の記事で紹介しています。(意外な場所もあるので参考になると思います)
-

-
受験生や高校生におすすめの勉強場所10選【集中力アップ】
続きを見る
関連記事:受験生や高校生におすすめの勉強場所10選【集中力アップ】
逆転合格できた戦略とは?
私は宅浪時代に1日7時間しか勉強しませんでしたが、それでも合格できたのは「戦略的に」勉強したためです。単に効率的に勉強するだけでなく、いつ・何を・どれくらい勉強するかまで含めて考えました。
戦略とは一言でいうと「志望校合格のために『時間・体力・金』というリソースをどの教科にどれだけ、どうやって注ぐか」です。
戦略を立てることは「勉強の仕方を勉強する」ということです。
特に底辺高校に通う受験生や志望校と偏差値のギャップのある受験生の皆さんは、限られた時間を効率的(=戦略的)に使わないと、合格の可能性が低くなってしまいます。
底辺高校からでも難関大学への逆転合格を可能とする「戦略」の立て方を、下記記事で詳しくご説明していますので合わせてどうぞ。
参考書ルートが9割
効率的な勉強法は、結局「どの参考書を、どの順番で勉強するか」が非常に重要だったりします。
一つの参考書が終わった後に、次にどの参考書で勉強するかって、結構悩むと思います。
同じレベルの参考書を選んでしまうと時間の無駄になりますし、レベルが高すぎる参考書を選んでしまうと解けない問題ばかりで非効率になります。
特に、塾や予備校に行かずに独学で勉強している受験生にとっては、参考書選びはかなり重要です。
以下の記事で、効率的に且つ着実に偏差値を上げる参考書ルートを科目別に解説しているので参考にご覧ください。
反省点(もし、もう一度受験するなら絶対にやっていること)
偏差値40の底辺高校から国立大学(それも旧帝大)に合格して非常に満足していますが、後悔していることもたくさんあります。
特に、以下の2点は今でも後悔していることです。
- 最初から志望校を絞る&理想を高くする
- 人から教われる環境を整える
順番にご説明します。
最初から志望校を絞る&理想を高くする
一番やっておけばと後悔していることは「最初から志望校を絞る&理想を高くする」ということです。
目標がはっきりと決まっていることで、そこに至るまでの過程(=戦略)が明確に定められます。
目標が曖昧だと効率が非常に悪いです。
当たり前すぎるので皆さんは既にやっているかもしれませんが、、、
また志望校は遠慮せず、自分が本当に行きたい大学に設定すべきです。
私は大阪大学に合格することができましたが、今から振り返ると最初からもっと高みを目指し、京都大学を志望校にしておけば良かったとかなり後悔しています。
「自分が〇〇大学なんて、、、」と絶対に思わないでください。
正しい戦略と勉強法と努力があれば、 必ず結果は付いてきます。
仮に夢が叶わなかったとしても、高い目標に向かって努力していると、その一歩手前のところは余裕でクリアできてしまうものです。
結果的に妥当な目標を定めるより、良い結果を得ることができます。
-

-
失敗談から学ぶ後悔しない大学選び【人生変わります】
続きを見る
関連記事:失敗談から学ぶ後悔しない大学選び【人生変わります】
人から教われる環境を整える
私は宅浪生であったため、誰にも頼ることができませんでした。
分からない問題があったり、解説を読んでも理解できない時も、誰にも頼ることができず一人で解決しなければなりませんでした。
詳しい人に聞けば一発で終わるのに、何時間も時間をかけて悩んでいたので非常に効率が悪かったです。
週一で良いので家庭教師をつけておくべきだったと非常に後悔しています。
宅浪生でなくても、学校の先生や予備校の講師が頼りにならないという人はいると思います。
そういう人は家庭教師を遠慮なくつけましょう。
今はオンライン家庭教師が発達しているので、塾より安価で且つオンラインなので気軽に利用することができます。
-

-
高校生・大学受験におすすめのオンライン家庭教師14社を徹底比較。ランキング形式で紹介
続きを見る
関連記事:高校生・大学受験におすすめのオンライン家庭教師14社を徹底比較。ランキング形式で紹介
逆転合格エピソードまとめ:底辺高校から国立大学の合格は可能
MARCHも関関同立も早慶も旧帝大も簡単です。
誰でも入れる大学ですので、みなさん希望を失わないでください。
底辺高校に通っていたとしても、難関大学に合格することは可能です。
私が身を持って証明します。
大事なのは、「継続」と「戦略」です。
実際に私は継続的に且つ戦略的に勉強したことで、偏差値40の底辺高校から歴代初となる大阪大学に逆転合格出来ました。
受験戦略を立てて、それに沿って継続的に勉強するだけで誰でも難関大学に合格出来ます。
この記事でご紹介した方法を是非参考にして頂き、第一志望合格というワクワクするような未来を掴み取ってください。
応援しています。










